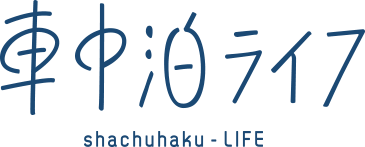DIYで木工品を制作したあとは【サンドペーパー】で仕上げましょう。
使い方&使う箇所を元大工が詳しく解説します。
サンドペーパーはDIYに必須道具。安い道具だから初心者は最初に買っておくといいよ!
目次
こんにちは、@車中泊ライフです。
皆さんはDIYで木材をカットしたときに後処理ってしてますか?
今回は、サンドペーパーでちょっと処理してあげると見た目も手触りも全然ちがいますよ、って話です。
YouTubeチャンネルには『DIY』の動画もあります!!
当ブログ『車中泊ライフ』のYouTubeチャンネル『車中泊ライフTV』には【DIYのハウトゥ動画】もあるので是非参考にしてみてくださいね!▼(チャンネル登録してくれると励みになります!)
サンドペーパーはDIYに必須です!
DIYには木材カットがつきものでして、自分で切るかホームセンターなんかのお店で切るかは人それぞれなんですけど、どちらにせよ、カットしたらサンドペーパーで一手間かけてあげると完成結果が変わってきます。
ついでに言うと、ケガの防止にもなったりするので持っておいて損はないです。
安いですしね。
それでは、どんなとき、どんな場所にサンドペーパーを使うかを説明していきます。
サンドペーパーの仕上げ処理についてご紹介
いくつかあるので、順を追って紹介していきます。
1・カットした小口(断面)の仕上げ処理
木材をカットすると、よっぽど切れる刃で切らないと必ず「バリ」というものが断面に出ます。
「バリ」とは、切断面にささくれたったケバケバしたやつです。
これ、そのままにして使っても問題ないのですが、手で持つときなどの力加減によっては手に刺さったりするんですよ。
このケバケバしたやつをサンドペーパーで擦って処理してあげると、キレイに取れて指に刺さる危険を防ぐことができます。
細い木のトゲって刺さるとなかなか取れないんですよね。
木材の色が肌と同系色だと見つけづらいのでなおさら抜けないんです。
なので、サンドペーパーでちゃちゃっと処理して体に優しい制作物に仕上げましょう。
2・使う木材の角を面取ってあげよう
木材の角についての説明はいらないと思いますが、写真の方がわかりやすいと思うので一応載せておきます。
▲ここですね。
ここをサンドペーパーで擦って少し丸み帯びさせる、もしくはほんの少し平らにしてあげることを「面を取る」といいます。
なぜこんな処理をするかというと、ぶつけたときの破損防止や手触りを良くするためなのですが、もう一つ、怪我を防止する効果もあります。
エッジの効いた木材の角というのは思ってるより切れ味が鋭いので、勢いよく人体でこすってしまうと普通に切れたりします。
自分も含め、その作ったものを使う人が怪我をしないことを考えた処理をしてあげることも一種の優しさなのではないでしょうか。
誰かに頼まれて何かをDIYするときには特に気をつけましょう!
3・面を磨いて手触りを良くしよう
木工のDIYで何かを作るとき、その対象のほとんどが「日常で使う・生活のなかで近くにある」ものかと思いますので、どうせだったら、なるべく手触りが良くて使っていて気持ちのいい木製品にするべきだとぼくは考えます。
使う木材の大きい面は使用上ひとが触れる機会が多いので、「この箇所は肌に触れるだろうな」といったところにほんの少し手間をかけてあげることで、温もりのある優しい触り心地を演出することができます。
使う木材にもよりますが、ベニヤ板なんかは表面に目視が難しい細かいバリがピョンピョン浮いている場合も多いので、撫でてみて「あ、ちょっと引っかかるな」と感じたら、サンドペーパーで表面をササっと磨いてバリを取ってあげてください。
バリを除去してあげたあとは、ワックスなんかで仕上げてあげるとより手触りが良くなるのでオススメですよ。
サンドペーパーはDIYに必須道具。安い道具だから初心者は最初に買っておくといいよ!、のまとめ
職業柄、ちょっとした木のトゲが手に刺さるのは日常茶飯事なのですが、かなり細いトゲであっても刺さりかたによってはいつまでも痛みが取れない、なかなか抜けない、なんてことがあるので、皆さんがDIYで作るものではなるべく研磨して手触りをよくしたほうがいいんじゃないかなぁと思っています。
作った当人ならまだしも、それを使うご家族の方が痛い思いをするのは見たくないですからね。

ではまた!
最新情報をお届けします
Twitter で車中泊ライフをフォローしよう!
Follow @shachuhaku_life